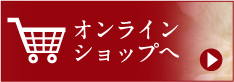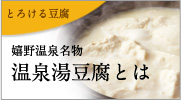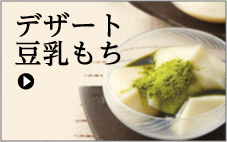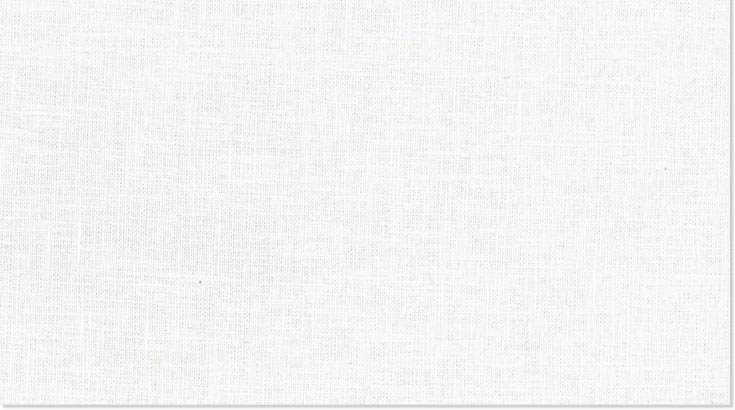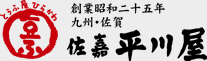日本三大美肌の湯として知られる九州の名湯、
嬉野温泉の名物で、調理水を用いて
湯豆腐にすることにより豆腐が溶け出し、
汁が白濁してやわやわと淡雪のような
優しい食感が楽しめます。
嬉野温泉の名物で、調理水を用いて
湯豆腐にすることにより豆腐が溶け出し、
汁が白濁してやわやわと淡雪のような
優しい食感が楽しめます。

トップ > 温泉湯豆腐とは

※写真はイメージです。

温泉湯豆腐はなぜとろける?
嬉野温泉名物の温泉湯豆腐は、ただの湯豆腐ではありません。豆腐を鍋で煮るのは湯豆腐と同じですが、温泉湯豆腐の場合、鍋の中に入っているのはお湯ではなく温泉水。するとなぜかコトコト炊いているうちに、豆腐の表面が溶け出して温泉水は豆乳のように白く濁ってきます。角のとれた豆腐は、食感も味わいも一段とまろやかに。白濁した温泉水は、コクがあり、一緒にすするとさらに深い味わいとなります。しかし、なぜこんなに不思議な湯豆腐ができるのでしょうか。
とろける秘密は、嬉野温泉のお湯。
佐賀県の嬉野温泉は、肥前風土記にも登場する歴史ある温泉で、江戸時代には長崎街道の宿場町として栄えたところ。ぬめりのあるお湯はナトリウムを多く含む重曹泉で、近年、この弱アルカリ性のお湯が角質化した肌をなめらかにするとして、斐乃上温泉(島根)と喜連川温泉(栃木)と共に「日本三大美肌の湯」に選ばれ、注目を浴びています。実はこのつるつるすべすべの美肌の湯が、なにを隠そう、温泉湯豆腐の生みの親。弱アルカリ性の温泉水が、豆腐をとろとろにとろけさせるのです。
江戸時代から親しまれてきた温泉湯豆腐
この温泉湯豆腐は、長崎街道(江戸時代に整備された脇街道の一つ)の宿場町時代にはすでに旅人に供されていたそうです。現代の話でいえば、温泉が配管されている温泉街中心部の家々では、湯豆腐といえばイコール温泉湯豆腐のことで、とろけない湯豆腐を見て反対に驚いた人もいるほど。各温泉旅館でも朝食には必ず温泉湯豆腐が出てきますし、温泉街の飲食店でも定番メニューになっています。その地元限定の名物料理が全国区になったのは、嬉野温泉と同質の温泉とうふ用調理水が開発されてから(ちなみに温泉水は販売が禁止されています)。今では地元以外のみなさまにも手軽にとろける温泉湯豆腐を楽しんでいただいております。佐嘉平川屋では、温泉湯豆腐用により溶けやすくよりふんわりとした食感が楽しめるように工夫した木綿豆腐を、温泉とうふ用調理水とセットで販売いたしております。まずは添え付けの胡麻だれで。あとはお好みでぽん酢、醤油、さまざまな薬味で召し上がってください。魚介類や野菜を入れてもおいしくいただけます。

一度で二度おいしい、ヘルシーな嬉野温泉名物 温泉湯豆腐
◆ 温泉湯豆腐を作る
1.温泉とうふを適当な大きさに切ります。
※調理水だけを先に火にかけると美味しく作れません。
※調理水だけを先に火にかけると美味しく作れません。

2.調理水と温泉とうふを
鍋に入れてから強火にかけます。
鍋に入れてから強火にかけます。
3.温泉とうふが溶け出し
調理水が白く濁ってきたら
弱火にします。
調理水が白く濁ってきたら
弱火にします。
4.調理水に温泉とうふの旨みが広がり
白濁したスープ状になってきたら、
豆腐の表面がとろ〜りとなってきます。
そのとろ〜りが食べ頃の合図です。
ぽん酢や胡麻だれでお召し上がりください。
※野菜は調理水が完全に白濁し、温泉湯豆腐が出来上がったころに
入れてお楽しみください。
白濁したスープ状になってきたら、
豆腐の表面がとろ〜りとなってきます。
そのとろ〜りが食べ頃の合図です。
ぽん酢や胡麻だれでお召し上がりください。
※野菜は調理水が完全に白濁し、温泉湯豆腐が出来上がったころに
入れてお楽しみください。
◆ 雑炊を作る
5.残った旨みスープにご飯を入れ
お塩で味を調えると
「佐嘉湯の華雑炊」の出来上がり。
※卵やのりを入れるとさらに美味しくいただけます。
お塩で味を調えると
「佐嘉湯の華雑炊」の出来上がり。
※卵やのりを入れるとさらに美味しくいただけます。
◆ アイデア次第で美味しさ色々
温泉湯豆腐は楽しみ方もいろいろ。
とってもヘルシーなきのこ鍋、ちょっと豪華に海鮮鍋、
子供も喜ぶつみれ鍋、残ったスープで豚しゃぶなど。
とってもヘルシーなきのこ鍋、ちょっと豪華に海鮮鍋、
子供も喜ぶつみれ鍋、残ったスープで豚しゃぶなど。
 |
 |
 |
 |
◆ 嬉野温泉名物 温泉湯豆腐はこちらで